 お月見の由来や意味って何だろう?
お月見の由来や意味って何だろう?
9月や10月の秋にはお月見をされる機会もあると思いますが、いったいいつからお月見をやるようになったのか?

どんな歴史があって今のようなお月見が定着したのか不思議ですよね。
また、昔の人も今のようなお月見のスタイルで楽しんでいたんだろうか?
考えてみると、お月見について知りたいことがたくさん出てくると思います。
そこで今回は、
お月見の由来や意味とは何なのか。
またお月見の歴史や風習、お供え物の月見団子やすすきの意味。
お月見に必要な物や楽しみ方など、その時代ごとのいろんなお月見のスタイルをまとめてみました。
お月見の由来や意味とは?

9月になるとお月見を楽しむ時期として知られていますよね。
その中でも「中秋の名月」と言う言葉も聞くと思いますが、旧暦8月15日に訪れる満月のことを指しています。

このお月見の由来や歴史ですが、遠く平安時代にまでさかのぼります。
実は、中秋の名月のお月見の由来は、中国の「中秋節」という習慣が伝わったこととされています(諸説あります。)
そしてこれが日本に伝わってきたのは、平安時代と言われていますね。
この中秋の名月は、別名で
- 十五夜(じゅうごや)
- 望月(もちづき)
- 望(ぼう)
- 三五の月(さんごのつき)
- 芋名月(いもめいげつ)
- 名月(めいげつ)
- 満月(まんげつ)
このように呼ばれることもあります。
「芋名月」などと呼ばれるのは、この時期に収穫される「芋」をお供えし収穫を感謝したという意味が込められています。
お月見の歴史や風習は?
日本でも平安時代の前から月を眺めて楽しむことはあったようですが、
「月を眺めながら詩を詠む」
といった楽しみ方を始めたのが平安時代と言われており、醍醐天皇時代に月見の宴を開いたというのが記録として残されているようです。
ですので、当時は「貴族の間での楽しみ」といった感覚で、一般庶民には浸透はしていなかったようです。
お月見の風習と江戸時代

このお月見の風習は、江戸時代に入ってから農民や武士などの間にも浸透し広まったと言われています。
今は月見団子片手に眺めるような楽しみ方ですが、江戸時代は月見団子ではなく、この時期に収穫される「芋」をお供えし収穫を感謝したと言われています。
そのことから、別名「芋名月」とも呼ばれてきました。
そして、この芋の収穫が終わると、いよいよお米の収穫の時期も近づいてきます。
そこで月へのお供え物をお米で団子にして作り、豊作をお祈りしていたと言われています。
お月見はこのような歴史とともに移り変わっていき、今のように月見団子というものが定着したのではないかと言われていますね。
また、この月見団子は満月もイメージして作られたと言われていて、健康長寿の意味も込められていたと考えられています。
お月見のススキの意味
お月見で月見団子は欠かせませんが、よくお団子を用意する時にススキもセットで合わせますよね。
あのお月見のススキにも意味があります。
実は、本来はススキではなく「お米の稲穂」が月の神様の依り代と言われています。

ただ、この時期にはお米の稲穂がなかったため、その代用として形に似ているススキを使ったと言われています。
また、ススキには魔除けの意味も込められており、お祈りには最適だったのですね。

ススキとお団子の位置ですが、
- 月から見て左側:ススキや稲など
- 月から見て右側:月見団子
このような位置関係にして備えるといいようです。
月見団子とウサギの意味

「ウサギがお月様でお餅をついている」というのは、さまざまな説がありますが、インドの「ジャータカ神話」のお話が有名です。
帝釈天(たいしゃくてん)と呼ばれる神様が、みすぼらしい老人に姿を変えて倒れたふりをし、キツネとサル、ウサギに食べ物を乞いました。
キツネとサルは老人に食べ物をあたえましたが、ウサギには何もありません。
そこで考えたウサギは
「私を食べて下さい」
と言い残し火の中へ飛び込み、自分を老人に捧げました。
これを見た帝釈天は感動し、ウサギの姿を月に残したと言われています。
また、これが日本に伝わったときには、日本の「望月(もちづき)」と合わさって、
と、言われています。
*望月というのは「満月」「十五夜」のことです。
これには他にも説が色々あったり、国によっても伝説が違うようですね。
月見団子の数の意味は?
実は月見団子には「数」についてもいくつか説があります。
といった説や、
- 1年の月の数の12か月分として、12個乗せる
- また、閏月のある年は13個乗せる
こういった説があります。
また、乗せ方も
12個(下段に9個、上段に3個)
13個(下段に9個、上段に4個)
15個(下段に9個、中段に4個、上段に2個)
このように決まっているとも言われていますね。
まあ、今では特にそこまでのこだわりはないと思いますが、もし何個か迷った時は参考にしてください。
お月見には何をする?必要なものや楽しみ方
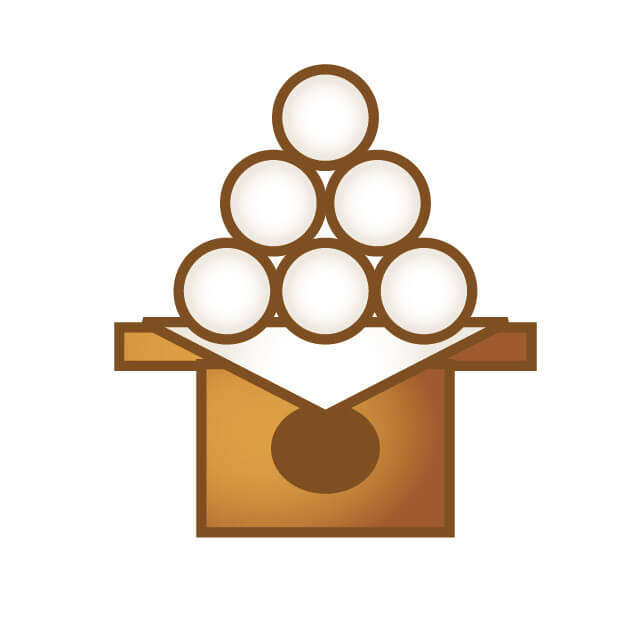 お月見って何するものなのか、改めて振り返ってみると色々と変化もあります。
お月見って何するものなのか、改めて振り返ってみると色々と変化もあります。
- お月見を楽しむために必要なものは何なのか?
- 今ではどんな楽しみ方があるのか?
オーソドックスなお月見の楽しみ方だと、その時に必要なものは「月見団子」ですね。
もし飾り付けなどをするのであれば、
月見団子を乗せる台(三方)
ススキ
コレがあれば雰囲気も出るし、良いお月見が出来るでしょう。
あとは芋名月ということで、里芋などをお供えする風習もありましたが、なにかお芋の料理などもあると良いかもしれませんね。
今ではお月見の楽しみ方も色々あり、
- 月見団子を作って楽しむ。
- 月見の料理を作って楽しむ
- 飾り付けを楽しむ。
- お酒を楽しむ。
- 子供と一緒に眺めて楽しむ。
- 写真を撮って楽しむ。
- 写真を撮ってSNSなどで共有する。
- 照明を消し、和ろうそくやキャンドルを使い、月明かりを楽しむ。
- 山の上まで出かけるなど、場所を変えて楽しむ。
- スズムシ、マツムシ、コオロギなどの虫の音を楽しむ
- 赤ちゃんアートで楽しむ。
いろんなお月見の楽しみ方がありますね。
赤ちゃんアート可愛い写真を?秋のお月見編
他にもお月見の楽しみ方は色々あると思います。
「見て楽しむ」「聞いて楽しむ」「食べて楽しむ」といったように、色々なお月見の楽しみ方がありますね。
あとがき
お月見の由来や意味は何なのか。
またお月見の歴史や風習、お供え物の月見団子やすすきの意味。
お月見に必要な物や楽しみ方など、その時代ごとにいろんなお月見のスタイルがあるんですね。
秋の夜長に涼しい風に当たりながら月見をして、月見団子片手にお酒を飲むなんて言う余裕を持ちたいですね。
お月見には月見団子や十五夜など様々なキーワードがありますが、これらの意味や由来を知っておくと月見がさらに楽しめるようになります。
そんなお月見を100倍楽しむためにたくさんの豆知識をまとめました。
非常に興味深い話がたくさんあるので、ぜひ気になる記事をご覧になってください!
そんなお月見ですが、実は毎年、中秋の名月の日付は変わるんです。

じゃあ今年はいつなのか、知っておかないとキレイなお月さまでの月見が楽しめませんよね。
そんな今年の月見の時期をコチラのページでまとめています。
中秋の名月以外にも、9月10月にはお月見に絶好の期間があります。
お月見に見どころの日も一緒にまとめているので、こちらもぜひチェックしてください。



コメント